YouTube料理動画の撮り方を徹底解説!美味しそうに見せる撮影テクニックとは。この記事では、料理動画の基本撮影技術(カメラ位置・アングル・ライティング)、4つの主要アングル(真俯瞰・斜め俯瞰・目線・手元アップ)とその使い分け、美味しそうに見せる7つのテクニック(自然光活用・色の鮮やかさ・湯気や動き・シズル感・盛り付け・背景整理・テンポの良い編集)、音の重要性(調理音・ASMR効果)、必要機材(スマホでも可能・三脚・照明・マイク)、初心者から上級者向け機材選定、編集のポイント(カット・速度調整・テロップ・BGM)、よくある失敗と対処法まで網羅した実践ガイドです。
なぜ料理動画の「撮り方」が成功を左右するのか
「料理が得意だからYouTubeを始めたい」「レシピを多くの人に届けたい」こうした思いで料理チャンネルを始める人は多いですが、実際に成功するかどうかは「料理の腕」だけでなく、「撮り方」に大きく左右されます。同じ料理でも、撮り方次第で美味しそうにも、まずそうにも見えるからです。
料理動画は、YouTube内でも特に人気の高いジャンルです。世界的に有名な料理チャンネル(Tasty、クラシル、デリッシュキッチン、きまぐれクックなど)は、数百万から数千万の登録者を抱えています。これらのチャンネルに共通するのは、料理の腕前だけでなく、視聴者が「作ってみたい」「美味しそう」と思わせる撮影技術です。
料理動画の撮り方で重要なのは、視覚的な美味しさの演出です。人間は、実際に食べる前に、まず目で「美味しそう」と判断します。湯気の立ち上る様子、ジュージューと焼ける音、艶やかなソースが絡む瞬間、断面から溢れる肉汁など、これらを効果的に撮影することで、視聴者の食欲を刺激し、チャンネル登録や再生回数の増加につながります。
また、料理動画は「分かりやすさ」も重要です。視聴者は、レシピを学びたい、作り方を知りたいという明確な目的を持っています。手順が見やすく、材料や分量が分かりやすく、失敗しないコツが伝わる撮影をすることで、視聴者の満足度が高まり、リピーターが増えます。
さらに、料理動画は他のジャンルと比較して、機材や技術のハードルが高めです。料理という動きのある被写体を、限られたキッチンスペースで、美味しそうに撮る。これには、適切なカメラアングル、ライティング、音声、編集などの総合的な技術が必要です。しかし、基本を理解すれば、スマホ一台でも十分に魅力的な料理動画を作れます。
この記事では、YouTube料理動画の撮り方を、初心者にも分かりやすく、体系的に解説します。基本的な撮影技術、カメラアングルの使い分け、美味しそうに見せるテクニック、必要な機材、編集のポイント、よくある失敗と対処法まで、実践的な情報を提供します。この記事を読み終える頃には、あなたも魅力的な料理動画を撮影できるようになっているはずです。
料理動画撮影の3つの基本要素
まず、料理動画撮影の基本を理解しましょう。
基本要素1:カメラの位置とアングル
料理動画では、カメラの位置が最も重要です。
真上から撮る(真俯瞰)として、作業台全体を見渡せ、手の動きや材料の配置が分かりやすいです。最も一般的なアングルです。
斜め上から撮る(斜め俯瞰)として、料理の立体感が出て、より美味しそうに見えます。完成品の撮影に適しています。
目線の高さで撮るとして、臨場感があり、視聴者が一緒に料理している感覚を味わえます。
手元をアップで撮るとして、細かい技術や作業を見せたい時に有効です。包丁さばき、卵の割り方など。
カメラを固定として、料理動画では、カメラを固定することが基本です。手持ちでは、手ブレが発生し、見にくくなります。必ず三脚やスマホスタンドを使います。
基本要素2:ライティング(照明)
料理を美味しそうに見せるには、適切な光が不可欠です。
自然光が最強として、窓際で撮影すると、柔らかく自然な光が当たり、料理が美味しそうに見えます。特に、朝〜昼間の光が理想的です。
直射日光は避けるとして、直射日光は強すぎて、影が濃くなります。レースカーテン越しの光が理想です。
照明を追加として、夜間や自然光が不足する場合、LEDライトを追加します。複数の角度から照らすと、影が柔らかくなります。
影の調整として、濃い影は料理を美味しく見せません。レフ板(白い紙やボードでも可)を使って、影を明るくします。
色温度として、暖色系(3000〜4000K)の光が、料理を温かく美味しそうに見せます。寒色系(5000K以上)は、冷たい印象になります。
基本要素3:音声と環境音
料理動画では、音も重要な要素です。
調理音として、ジュージュー焼ける音、切る音、混ぜる音など、調理の音は食欲を刺激します。これらを効果的に録音します。
ナレーションとして、作り方を説明するナレーションを入れる場合、クリアで聞き取りやすい音質が必要です。
BGMとして、料理の雰囲気に合ったBGMを選びます。明るく軽快な曲、落ち着いたカフェ風の曲など。
環境ノイズの削除として、冷蔵庫の音、エアコンの音など、不要なノイズは録音時に注意するか、編集で削除します。
これら3つの基本要素を押さえることで、料理動画の質は大きく向上します。
4つの主要カメラアングルと使い分け
料理動画で使われる主要なアングルを詳しく解説します。
アングル1:真俯瞰(真上から)
最も一般的で、重要なアングルです。
メリットとして、作業台全体が見渡せる、手の動き、材料の配置が分かりやすい、視聴者が作り方を理解しやすい、複数の材料や道具を同時に映せるなどがあります。
適した場面として、材料の準備、切る作業、混ぜる作業、盛り付け、全体の工程を見せたい時などです。
撮影方法として、カメラを作業台の真上に設置します。三脚のアームを伸ばす、天井から吊るす、専用の俯瞰スタンドを使うなどの方法があります。
注意点として、カメラが落下しないよう、しっかり固定します。真上からだと顔が映らないため、ナレーションや手元で個性を出します。
アングル2:斜め俯瞰(斜め上から45度前後)
料理を立体的に、美味しそうに見せるアングルです。
メリットとして、料理に立体感が出る、盛り付けた料理が美しく見える、背景も少し映り、雰囲気が伝わる、顔を映すこともできるなどがあります。
適した場面として、完成品の撮影、料理を器に盛る瞬間、焼き上がった瞬間、美しく盛り付けた状態などです。
撮影方法として、カメラを作業台の斜め上、45度前後の角度に設置します。高さは1〜1.5メートル程度が一般的です。
注意点として、背景が映るため、キッチンを整理整頓しておきます。不要なものは映らないようにします。
アングル3:目線の高さ(アイレベル)
視聴者と同じ目線で、臨場感を出すアングルです。
メリットとして、一緒に料理している感覚、臨場感がある、鍋の中、フライパンの様子が見やすい、顔を映せる(顔出しする場合)などがあります。
適した場面として、炒める、煮る、焼くなど、鍋やフライパンでの調理、味見をする瞬間、話しかけるような演出などです。
撮影方法として、カメラを自分の目の高さに設置します。コンロの前、カウンター越しなど。
注意点として、手やフライパンがカメラに近すぎると、ピントが合わなくなります。適切な距離を保ちます。
アングル4:手元アップ(クローズアップ)
細かい作業を見せるアングルです。
メリットとして、細かい技術が伝わる、プロの技を見せられる、視覚的なインパクトがある、断面、質感を詳しく見せられるなどがあります。
適した場面として、包丁さばき、卵の割り方、生地をこねる手つき、断面を見せる(切った瞬間)、とろける瞬間などです。
撮影方法として、カメラを手元に近づけます。マクロモードや、カメラの最短撮影距離に注意します。
注意点として、アップにしすぎると、全体が見えなくなります。適度な距離を保ちます。ピントが合わない場合、カメラを少し離します。
アングルの切り替え
魅力的な料理動画は、これらのアングルを効果的に切り替えています。
基本は真俯瞰として、メインのカメラは真俯瞰に固定し、全工程を撮影します。
重要な場面でアップとして、包丁で切る瞬間、焼き色がつく瞬間など、重要な場面でアップのカットを挿入します。
完成品は斜め俯瞰として、完成した料理は、最も美しく見える斜め俯瞰で撮影します。
複数カメラの活用として、可能であれば、真俯瞰と斜め俯瞰、または真俯瞰と手元アップの2台体制で撮影すると、編集で切り替えられて便利です。
美味しそうに見せる7つの撮影テクニック
料理を美味しそうに撮影するための具体的なテクニックです。
テクニック1:自然光を最大限に活用
自然光は、料理撮影の最強の武器です。
窓際で撮影として、キッチンが窓際にない場合、作業台を窓際に移動させます。自然光が入る場所で撮影します。
時間帯として、午前中〜昼過ぎの光が、明るく柔らかいです。夕方の光は赤みが強く、料理によっては合わないことがあります。
レースカーテン越しとして、直射日光は避け、レースカーテン越しの柔らかい光を使います。
逆光を避けるとして、窓を背にすると、料理が暗くなります。窓からの光が、料理に当たるように配置します。
テクニック2:色を鮮やかに
料理の色は、美味しさの重要な要素です。
ホワイトバランスとして、カメラのホワイトバランスを適切に設定します。黄色っぽい、青っぽいなど、色が不自然にならないよう調整します。
彩りの工夫として、料理自体に彩りを加えます。パセリ、レモン、トマトなど、緑、黄、赤の色を加えると、視覚的に美味しそうになります。
白い器として、料理の色を引き立てるには、白い器が最も効果的です。
編集での調整として、編集時に、彩度を少し上げる、明るさを調整するなどで、色を鮮やかにできます。ただし、やりすぎは不自然です。
テクニック3:湯気や動きを撮る
静止画ではなく、動きがあることが動画の強みです。
湯気として、湯気は「温かい」「出来立て」を伝えます。黒い背景だと湯気が見えやすいです。逆光気味に撮ると、湯気が強調されます。
注ぐ瞬間として、ソースをかける、ドレッシングをかける、飲み物を注ぐなど、液体の動きは視覚的に美しいです。
ジュージュー音として、フライパンで焼く音、揚げる音など、動きと音を一緒に撮ります。
スローモーションとして、チーズが伸びる、断面から肉汁が出るなど、スローモーションで撮影すると、インパクトがあります。
テクニック4:シズル感(食欲をそそる質感)
シズル感とは、食べ物の瑞々しさ、艶、美味しそうな質感のことです。
油や水分として、適度な油や水分が、料理を艶やかに見せます。サラダにはオイルを少し足す、肉には照りを出すなど。
光の反射として、器やグラスに光が反射すると、高級感が出ます。
アップで質感として、肉の繊維、野菜のシャキシャキ感、クリームの滑らかさなど、質感をアップで撮ります。
テクニック5:盛り付けと器の選定
盛り付けは、料理の印象を大きく左右します。
高さを出すとして、平らに盛るより、少し高さを出すと、立体的で美味しそうに見えます。
余白を残すとして、器いっぱいに詰め込まず、適度な余白を残します。
彩りのバランスとして、緑、赤、黄色など、色のバランスを考えます。
器の選定として、料理に合った器を選びます。和食なら和食器、洋食なら洋食器が基本ですが、あえて外すことで個性も出せます。
テクニック6:背景の整理整頓
料理以外の部分も、映像の一部です。
キッチンを片付けるとして、撮影前に、映る範囲のキッチンを片付けます。不要なものは映らないようにします。
シンプルな背景として、背景はシンプルな方が、料理が引き立ちます。白い壁、木のまな板、布など。
統一感として、器、カトラリー、布巾などの色やスタイルに統一感を持たせると、プロっぽくなります。
テクニック7:テンポの良い編集
撮影だけでなく、編集も重要です。
無駄をカットとして、同じ作業の繰り返し(玉ねぎを全部切る様子など)は、一部だけ見せて、残りはカットします。
速度調整として、時間のかかる作業(煮込む、冷やすなど)は、早送りにします。
リズムとして、音楽に合わせてカットすると、心地よいリズムが生まれます。
音の重要性:料理動画における音声戦略
料理動画では、音が視聴体験の50%を占めます。
調理音の録音
料理の音は、食欲を刺激します。
重要な調理音として、ジュージュー焼ける音、切る音(トントン)、混ぜる音、揚げる音、沸騰する音、パリパリ割る音などがあります。
録音方法として、カメラの内蔵マイクでも録音できますが、専用のマイク(ピンマイク、ショットガンマイクなど)を使うと、より明瞭に録音できます。
近づけるとして、重要な音は、マイクを近づけて録音します。例えば、切る音を録音する時は、マイクをまな板に近づけます。
ノイズを減らすとして、冷蔵庫、エアコン、換気扇など、不要なノイズ源は可能な限り止めます。
ASMRとしての調理音
ASMR(Autonomous Sensory Meridian Response)として、心地よい音を聞くことで、リラックス効果を得られる現象です。料理の調理音は、ASMR効果が高いです。
音だけの動画として、あえてナレーションやBGMを入れず、調理音だけの動画も人気があります。静かな環境で、料理の音を堪能できます。
高音質で録音として、ASMR効果を狙う場合、高音質なマイクでの録音が重要です。
ナレーションの録音
作り方を説明するナレーションです。
ナレーションのスタイルとして、撮影しながら話す(同時録音)、撮影後に別途録音する(アフレコ)の2つの方法があります。アフレコの方が、音質が良く、言い間違いを修正できます。
明瞭な発音として、聞き取りやすく、はっきりと話します。早口すぎず、遅すぎず。
マイクの選定として、USB マイク、ピンマイクなど、クリアに録音できるマイクを使います。スマホやカメラの内蔵マイクは、距離が遠いと音質が悪くなります。
ノイズ除去として、編集ソフトでノイズ除去を行います。
BGMの選定
料理動画に合ったBGMを選びます。
明るく軽快な曲として、朝食、お弁当、簡単レシピなどに合います。
落ち着いたカフェ風の曲として、ゆっくり丁寧な料理、おしゃれな料理に合います。
和風の曲として、和食に合います。琴、尺八、三味線などの音色。
音量バランスとして、BGMは、ナレーションや調理音を邪魔しない音量に調整します。BGMが大きすぎると、うるさく感じます。
著作権フリーとして、必ず著作権フリーの音楽を使います。YouTube Audio Library、Epidemic Sound、Artlist などがあります。
必要な機材:初心者から上級者まで
料理動画撮影に必要な機材を、レベル別に紹介します。
初心者セット(予算1〜3万円):スマホで始める
スマホでも、十分に魅力的な料理動画を撮影できます。
スマホ(既に持っているもの)として、最近のスマホは、カメラ性能が非常に高いです。iPhone、Androidの中〜上位機種なら十分です。
三脚・スマホスタンド(2,000〜5,000円)として、カメラを固定するために必須です。俯瞰撮影用のスタンド、テーブル三脚などがあります。
照明(3,000〜10,000円、オプション)として、自然光が不足する場合、LEDリングライトやパネルライトを追加します。
ピンマイク(2,000〜5,000円、オプション)として、ナレーションを録音する場合、ピンマイクがあると音質が向上します。
このセットで、十分に始められます。多くの人気料理チャンネルも、最初はスマホから始めています。
中級者セット(予算5〜15万円):一眼カメラやミラーレスカメラ
より高画質、より表現力のある撮影がしたい場合です。
ミラーレスカメラ・一眼レフ(5〜10万円)として、Sony α6400、Canon EOS Kiss M2、Nikon Z50などが人気です。背景のボケ、色の表現力が格段に向上します。
レンズとして、標準ズームレンズ(キットレンズで十分)、マクロレンズ(手元のアップ撮影に有効)などがあります。
三脚・俯瞰スタンド(5,000〜20,000円)として、カメラ用の三脚、俯瞰撮影用のアームスタンドなどがあります。
照明(5,000〜30,000円)として、2灯セット、3灯セットのLEDライトで、プロ並みのライティングが可能です。
マイク(5,000〜20,000円)として、ショットガンマイク、ピンマイクなど、用途に応じて選びます。
上級者セット(予算20万円以上):プロ品質
本格的に料理動画を仕事にする場合です。
フルサイズミラーレスカメラ(15〜30万円)として、Sony α7 IV、Canon EOS R6などです。さらに高画質、高感度での撮影が可能です。
複数台のカメラとして、真俯瞰用、斜め俯瞰用、手元アップ用など、複数台のカメラを同時に回すことで、編集の自由度が上がります。
プロ用照明として、ソフトボックス、アンブレラなど、プロが使う照明機材で、完璧なライティングが可能です。
高音質マイクとして、Rode VideoMic Pro、Zoom H6などの高音質録音機材です。
スライダー・ジンバルとして、カメラを滑らかに動かす機材です。動きのある映像が撮影できます。
どのレベルから始めるべきか
初めての方は、スマホと三脚から始めることを強くおすすめします。理由として、初期投資が少ない、操作が簡単、持っているものを活用できる、撮影の基本を学べるなどがあります。
高い機材を買っても、撮影技術がなければ、良い動画は作れません。まずスマホで基本を学び、チャンネルが成長してから、より良い機材に投資することが賢明です。
編集のポイント:撮影素材を料理動画に仕上げる
撮影した素材を、魅力的な動画に編集します。
基本的な編集の流れ
素材の整理として、撮影した全ての素材を、編集ソフトに取り込みます。
不要部分のカットとして、失敗、言い間違い、長すぎる作業などをカットします。
順序の整理として、料理の工程順に、素材を並べます。
アングルの切り替えとして、真俯瞰、斜め俯瞰、アップなど、複数のアングルを効果的に切り替えます。
音声の調整として、音量を揃える、ノイズを除去する、BGMを追加するなどを行います。
テロップの追加として、材料、分量、手順、ポイントなどをテロップで表示します。
テンポの調整
料理動画は、テンポが重要です。
無駄をカットとして、同じ作業の繰り返し、待ち時間(煮込む、冷やす)は、カットまたは早送りにします。
速度調整として、編集ソフトで、動画の速度を調整します。2倍速、4倍速などにすることで、時間を圧縮できます。重要な部分はゆっくり、または通常速度で見せます。
リズムとして、BGMのリズムに合わせてカットすると、心地よいテンポが生まれます。
テロップ・字幕の活用
テロップは、視覚的に情報を伝えます。
材料・分量として、動画の冒頭、または調理の各段階で、材料と分量をテロップで表示します。
手順・ポイントとして、「ここがポイント!」「注意:火加減は弱火」など、重要な情報をテロップで強調します。
読みやすさとして、フォントは読みやすいもの、文字は大きめ、背景とのコントラストを高める(白文字に黒縁など)ことを意識します。
表示時間として、視聴者が読める時間(最低3秒)は表示します。短すぎると読めません。
効果音の追加
適切な効果音は、動画を楽しくします。
調理音の強調として、切る音、焼く音などが小さい場合、編集で音量を上げるか、効果音を追加します。
効果音として、「ピコン」「ジャーン」など、ポイントを強調する効果音を追加します。ただし、使いすぎは逆効果です。
カラーグレーディング
色味を調整して、統一感と美味しそうな見た目を作ります。
明るさ・コントラストとして、全体の明るさを調整します。料理は、少し明るめの方が美味しそうに見えます。
彩度として、彩度を少し上げると、色が鮮やかになります。ただし、やりすぎると不自然です。
色温度として、暖色系に少し寄せると、温かみのある映像になります。
LUT(Look Up Table)として、編集ソフトによっては、プリセットの色味(LUT)を適用できます。
おすすめ編集ソフト
初心者向けとして、iMovie(Mac、無料)、DaVinci Resolve(無料)、Filmora(有料、約8,000円)などがあります。
中級者以上向けとして、Adobe Premiere Pro(有料、月額2,728円)、Final Cut Pro(Mac、買い切り36,800円)などがあります。
まずは無料ソフトで基本を学び、必要に応じて有料ソフトに移行することをおすすめします。
よくある失敗と対処法
料理動画撮影で、多くの人が陥る失敗とその対処法です。
失敗1:手元が暗い
自然光や照明が不足していると、料理が暗く、美味しそうに見えません。
対処法として、窓際で撮影する、照明を追加する、編集で明るさを調整する(限界あり)などがあります。
失敗2:手ブレ
手持ちで撮影すると、手ブレが発生します。
対処法として、必ず三脚やスタンドを使う、手持ちの場合、両手でしっかり持つ、編集ソフトの手ブレ補正機能を使う(画質が少し落ちる)などがあります。
失敗3:ピントが合わない
特にアップで撮影する時、ピントが合わないことがあります。
対処法として、カメラを少し離す、オートフォーカスを使う、タッチフォーカス(スマホ)で、ピントを合わせたい場所をタップする、マニュアルフォーカスで、手動で調整するなどがあります。
失敗4:音が小さい、聞こえない
カメラの内蔵マイクでは、距離が遠いと音が小さくなります。
対処法として、ナレーションは別途録音する(アフレコ)、ピンマイクを使う、編集で音量を上げる(ノイズも大きくなるため限界あり)などがあります。
失敗5:動画が長すぎる
必要な情報を全部入れようとして、動画が長くなりすぎることがあります。
対処法として、無駄をカットする、早送りを活用する、複雑なレシピは、複数の動画に分けることも検討するなどがあります。
理想的な長さとして、料理動画は、3〜10分が最も視聴されやすいです。
失敗6:背景が散らかっている
撮影に集中して、背景の片付けを忘れることがあります。
対処法として、撮影前に、必ず背景を確認し、片付ける、映る範囲を限定する(アングルの調整)、編集で背景をぼかす(一眼カメラの場合)などがあります。
失敗7:材料や分量が分からない
作り方は分かるが、材料や分量が分からないと、視聴者は作れません。
対処法として、動画の冒頭で、すべての材料と分量を表示する、調理の各段階で、テロップで分量を表示する、説明文に、材料リストを記載するなどがあります。
まとめ:撮り方の基本を押さえて魅力的な料理動画を
YouTube料理動画の撮り方について、基本的な撮影技術、カメラアングルの使い分け、美味しそうに見せるテクニック、音の重要性、必要な機材、編集のポイント、よくある失敗と対処法まで詳しく解説しました。
重要なポイントをまとめると、料理動画の成功は撮り方に大きく左右されること、基本は真俯瞰・斜め俯瞰・目線・手元アップの4つのアングルを使い分けること、美味しそうに見せるには自然光・色の鮮やかさ・湯気や動き・シズル感・盛り付け・背景整理が重要であること、調理音は食欲を刺激しASMR効果もあるため丁寧に録音すべきこと、初心者はスマホと三脚で十分始められ機材より技術が重要であること、編集ではテンポ・テロップ・効果音・カラーグレーディングで魅力を高められること、そして最も重要なのは継続的に撮影し試行錯誤しながら上達することです。
料理動画の撮影は、最初は難しく感じるかもしれませんが、基本を理解し、何度も撮影を重ねることで、必ず上達します。有名な料理チャンネルも、最初は拙い動画から始めています。完璧を目指すより、まず撮影して投稿し、視聴者の反応を見ながら改善していくことが成功への近道です。
技術的な部分も重要ですが、それ以上に大切なのは、料理への愛情と、それを伝えたいという情熱です。美味しそうに撮れた瞬間、視聴者から「作ってみました!」というコメントが届いた時の喜びは、何物にも代えがたいものです。
今日から始められることは、スマホと三脚を用意すること、窓際でテスト撮影してみること、好きな料理を一品撮影してみることです。完璧な動画を作ろうとせず、まず一歩を踏み出しましょう。あなたの料理が、誰かの食卓を豊かにし、笑顔を作る日が来ます。
より詳しく学びたい方へ
この記事は、AIラボコミュニティの運営者が執筆しています。
YouTube料理動画の撮影技術と運営戦略をはじめ、効果的な編集テクニック、機材選定、視聴者を惹きつける演出方法、継続的なチャンネル成長戦略について、さらに深く学びたい方のために、AIラボでは無料のコミュニティを運営しています。実際の料理チャンネルの成功事例や、撮影・編集のコツ、機材の使い方など、実践的な情報を仲間と共に学べる場として、気軽にご参加いただけます。
人生を豊かにする今しかできないAI革命時代の新しい稼ぎ方では、YouTubeチャンネルの立ち上げから収益化、そして継続的なコンテンツ制作まで、包括的な戦略を解説しています。料理チャンネルで収益を得る具体的な方法も紹介しています。
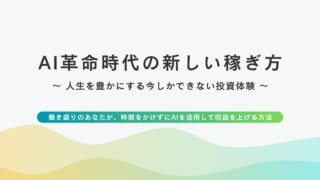
また、オープンチャット(あいラボコミュニティ:無料)では、同じように料理動画制作に取り組んでいる仲間たちと、撮影のコツを共有したり、機材の相談をしたり、お互いのチャンネルを応援し合ったりできます。美味しそうな料理動画を作り、共に成長できる環境です。



