YouTubeのカット編集を劇的に効率化する方法を徹底解説!編集時間の70%を占めるカット作業を最適化すれば、動画制作の生産性が3倍向上します。この記事では、キーボードショートカット(J・K・Lキーのタイムライン操作、I・Oキーのイン・アウト点設定)の活用、複数トラックの一括カット、無音部分の自動検出・削除、リップル削除による隙間自動詰め、プロキシ編集での動作軽量化、マーカー機能による編集ポイント事前記録など具体的テクニックを紹介。DaVinci Resolve・Adobe Premiere Pro・Final Cut Pro別のショートカット一覧、粗編集と精密編集の分離による効率的ワークフロー、「えー」「あー」などのフィラー音の素早い検出方法、集中力を維持する編集セッション管理まで網羅した実践ガイドです。
カット編集がYouTube制作時間の大半を占める理由
YouTube動画を作る際、最も時間がかかる作業は何でしょうか?多くのクリエイターが「カット編集」と答えます。10分の動画を作るために、数時間から丸一日かかることも珍しくありません。その時間の大部分を占めるのが、不要な部分を削除するカット作業です。
カット編集とは、撮影した素材から不要な部分(話し始める前の間、言い間違い、「えー」「あー」などのフィラー音、無駄な沈黙など)を削除し、テンポよく見やすい動画に仕上げる作業です。この作業は単純に見えますが、動画全体を何度も見返し、細かくカットポイントを見つけ、正確に切る必要があるため、非常に時間がかかります。
カット編集の効率が悪いと、動画1本の制作に膨大な時間がかかり、投稿頻度が下がります。投稿頻度が下がれば、YouTubeのアルゴリズムからの評価が下がり、チャンネルの成長が停滞します。また、編集に疲弊して、動画制作自体を続けられなくなるクリエイターも多くいます。
逆に、カット編集を効率化できれば、同じ時間で2倍、3倍の動画を制作でき、継続的な投稿が可能になります。編集にかける時間が減れば、企画や撮影、視聴者とのコミュニケーションに時間を使えるようになります。
この記事では、YouTubeのカット編集を劇的に効率化する具体的なテクニックを解説します。キーボードショートカットの活用、編集ソフトの便利機能、効率的なワークフロー、編集スピードを上げる思考法まで、初心者から中級者がすぐに実践できる情報を提供します。これらのテクニックを身につけることで、編集時間を半分以下にし、YouTube活動を持続可能なものにできます。
キーボードショートカット:編集速度を倍増させる基本
カット編集の効率化で最も即効性があるのが、キーボードショートカットの習得です。マウスでメニューをクリックする代わりに、キーボードだけで操作できれば、作業速度が2〜3倍になります。
絶対に覚えるべき基本ショートカット(共通)
ほとんどの編集ソフトで共通する基本的なショートカットがあります。
スペースキーは、再生と一時停止の切り替えです。最も頻繁に使う操作で、これだけでもマウスに手を伸ばす回数が激減します。
J・K・Lキーは、タイムライン操作の黄金トリオです。Jキーは逆再生(押すたびに速度が上がる)、Kキーは一時停止、Lキーは順再生(押すたびに速度が上がる)です。この3つを使いこなすと、再生ヘッドを素早く目的の位置に移動できます。
左右矢印キーは、1フレームずつ移動します。正確なカットポイントを見つける際に必須です。
I(イン点)とO(アウト点)キーは、カットしたい範囲の開始点と終了点を設定します。範囲選択が一瞬でできます。
Deleteまたはバックスペースキーは、選択した部分を削除します。
これらの基本ショートカットを使うだけで、編集速度が大幅に向上します。
主要編集ソフト別のショートカット一覧
DaVinci Resolve
- Ctrl+B(Win)/ Cmd+B(Mac):再生ヘッド位置でクリップを分割
- Ctrl+\(Win)/ Cmd+\(Mac):イン点からアウト点までを削除(リップル削除)
- Shift+Delete:削除して隙間を詰める
- Q:前の編集点に移動
- W:次の編集点に移動
Adobe Premiere Pro
- C:カミソリツール(分割)
- V:選択ツール
- Ctrl+K(Win)/ Cmd+K(Mac):再生ヘッド位置でカット
- Shift+Delete:リップル削除
- ; : 次の編集点に移動
- ‘ : 前の編集点に移動
Final Cut Pro
- Cmd+B:ブレード(分割)
- Delete:選択削除(自動的にリップル)
- Shift+Z:タイムラインを画面に合わせる
- Option+W:イン点からアウト点までを削除
ショートカット習得の効率的な方法
一度にすべてを覚えようとせず、段階的に習得します。
ステップ1:スペースキーとJ・K・Lキーの3つだけを1週間使い続ける ステップ2:I・O・Deleteキーを追加して1週間練習 ステップ3:分割とリップル削除のショートカットを追加
1ヶ月後には、手がショートカットを自然に覚え、意識せずに使えるようになります。
また、よく使うショートカットを付箋に書いてモニターに貼る、またはショートカット一覧表を印刷して手元に置くことで、素早く確認できます。
カスタムショートカットの設定
多くの編集ソフトでは、ショートカットをカスタマイズできます。
自分の手の位置や使用頻度に合わせて、ショートカットを再設定することで、さらに効率が上がります。例えば、最も頻繁に使う操作をホームポジション(A・S・D・F)付近のキーに割り当てるなどです。
ただし、標準のショートカットに慣れておくと、他の人のPCで作業する際や、チュートリアルを見る際に便利なため、最初は標準設定で習熟することをおすすめします。
効率的なカット編集ワークフロー
カット編集の作業プロセス自体を最適化することで、大幅な時短が可能です。
粗編集と精密編集の分離
一度にすべてを完璧に編集しようとせず、2段階に分けます。
第1段階:粗編集(ラフカット) 最初のパスでは、明らかに不要な部分だけを大胆にカットします。完璧を求めず、スピード重視で進めます。
目安として、10分の素材を30分〜1時間で粗編集します。言い間違いや大きな沈黙、明らかな失敗部分だけを削除します。細かい「えー」「あー」は後回しにします。
この段階では、2〜3倍速で再生しながら進めます。J・K・Lキーを活用し、高速で素材を確認します。
第2段階:精密編集(ファインカット) 粗編集が終わったら、通常速度で全体を見直し、細かい調整を行います。
「えー」「あー」などの小さなフィラー音を削除します。テンポを調整し、最適な間を作ります。カットのタイミングを微調整します(1〜2フレーム単位)。
この2段階アプローチにより、常に全体像を把握しながら編集でき、完璧主義による時間の無駄を防げます。
マーカー機能の活用
撮影または素材確認時に、編集ポイントをマーカーで記録しておくと、カット作業が劇的に速くなります。
素材を最初に見る際、カットが必要な場所でマーカー(M キーなど)を付けます。マーカーの色を使い分けます(赤:完全削除、黄:要確認、緑:重要な場面など)。
編集時は、マーカーをガイドにして素早くカットポイントに移動できます。素材を何度も見返す時間が大幅に削減されます。
複数トラックの一括カット
音声と映像、または複数のカメラアングルを同時に編集する場合、一括操作が重要です。
リンクされたクリップ(映像と音声が連動)を使用すれば、片方をカットすると自動的に両方がカットされます。
複数のビデオトラックがある場合、「すべてのトラックを選択」してからカットすることで、一度にすべてのトラックが同じ位置でカットされます。
これにより、映像と音声がずれるトラブルを防ぎ、編集ミスが減ります。
リップル削除の活用
通常の削除では、クリップを削除した後に空白(ギャップ)が残り、手動で詰める必要があります。
リップル削除(Ripple Delete)は、削除と同時に後続のクリップを自動的に前に詰める機能です。この機能を使うことで、削除→ギャップを埋める、という2ステップが1ステップになります。
ほとんどの編集ソフトで、Shift+Deleteまたは専用のリップル削除機能があります。これを習慣化すると、編集速度が大幅に向上します。
波形表示によるカット
音声の波形を見ながら編集すると、無音部分や小さな音を視覚的に判断でき、速度が上がります。
タイムライン上で波形表示を有効にします(多くのソフトで標準機能)。波形が小さい、またはフラット(無音)な部分は、削除候補です。
特に、話と話の間の沈黙、「えー」の前後の小さな息継ぎなどが視覚的に分かり、いちいち聞き直さなくても判断できます。
プロキシ編集で動作を軽快に
4K動画や長時間の素材を編集する場合、ソフトの動作が重くなることがあります。
プロキシ編集とは、元の高解像度動画の代わりに、低解像度の仮ファイル(プロキシ)を使って編集する方法です。
編集中は軽量なプロキシで作業し、最終的な書き出し時に元の高解像度動画に自動的に置き換わります。これにより、編集作業がスムーズになり、ストレスが減ります。
DaVinci Resolve、Premiere Pro、Final Cut Proなどの主要ソフトは、プロキシ編集に対応しています。
無音・フィラー音の自動検出と削除
カット編集で最も時間がかかるのが、「えー」「あー」などのフィラー音や無音部分を見つけて削除する作業です。これを自動化または半自動化できれば、大幅な時短になります。
無音部分の自動検出
多くの編集ソフトには、音声レベルが一定以下の部分を自動検出する機能があります。
DaVinci Resolveでは、「Timeline」→「Auto Align Clips」または「Silence Detection」機能を使います。設定した音量レベル以下の部分を自動的にマーカーまたはカットします。
Adobe Premiere Proでは、「Essential Sound」パネルの「Reduce Noise」や、サードパーティプラグインの「AutoCut」が使えます。
これらの機能を使うことで、長時間の無音部分を一括で検出・削除できます。
AutoCutプラグイン(Adobe Premiere Pro)
AutoCutは、AI技術を使って無音部分や「えー」「あー」を自動検出し、カットしてくれるプラグインです。
有料(約$30程度)ですが、編集時間を劇的に短縮できるため、コストパフォーマンスが非常に高いです。無音部分の自動削除、フィラー音の検出、繰り返し部分の削除、ズーム効果の自動追加などの機能があります。
特に、毎日のように動画を編集するYouTuberには強く推奨されます。
Descript:文字起こしベースの編集
Descriptは、音声を自動的に文字起こしし、テキストを編集することで動画が編集できる革新的なソフトです。
文字起こしされたテキストから不要な部分(フィラー音、言い間違いなど)を削除すると、自動的に動画もカットされます。視覚的に編集ポイントが分かるため、通常の編集より速く正確にカットできます。
月額料金がかかりますが、編集時間を大幅に短縮できる画期的なツールです。
手動でのフィラー音検出のコツ
自動ツールを使わない場合でも、効率的にフィラー音を見つける方法があります。
音声波形を表示し、小さな山(小さな音)を探します。「えー」「あー」は通常、話している部分より波形が小さいです。
2〜3倍速で再生しながら、耳で聞いてマーカーを付けます。通常速度より速く確認でき、フィラー音が強調されて聞こえやすくなります。
パターンを覚えると、視覚的に判断できるようになります(「あー」の前には小さな息継ぎ、その後に小さな波形など)。
息継ぎの処理
完全に無音の部分だけでなく、息を吸う音も削除するとテンポが良くなります。
ただし、すべての息継ぎを削除すると不自然になるため、長い息継ぎや目立つ息継ぎだけを削除します。
また、話と話の間の息継ぎは、自然な間として残すこともあります。機械的に削除せず、リズムを考えながら判断します。
効率を維持する編集環境とマインドセット
技術的なテクニックだけでなく、編集環境と精神的なアプローチも効率に大きく影響します。
デュアルモニターの活用
2つのモニターを使用すると、編集効率が大幅に向上します。
メインモニターにタイムラインと編集画面、サブモニターにプレビュー画面やオーディオメーターを表示します。画面を切り替える手間がなくなり、全体像を把握しながら作業できます。
予算に余裕があれば、デュアルモニター環境への投資は、編集ソフトや機材への投資より効果的な場合があります。
ポモドーロ・テクニックの応用
長時間連続で編集すると、集中力が落ち、ミスが増え、結果的に効率が下がります。
ポモドーロ・テクニック(25分作業+5分休憩)を取り入れることで、集中力を維持できます。タイマーをセットし、25分間は編集だけに集中します。5分休憩で席を立ち、目と体を休めます。4セット(2時間)後に長めの休憩(15〜30分)を取ります。
これにより、長時間の編集セッションでも疲労を抑え、一貫した品質を保てます。
テンプレートとプリセットの作成
同じスタイルの動画を繰り返し作る場合、テンプレートを作成します。
オープニング、エンディング、トランジション、テロップのスタイルなどをテンプレート化し、新しいプロジェクトで再利用します。毎回ゼロから作る必要がなくなり、時間が大幅に短縮されます。
また、よく使うエフェクトやカラーグレーディングをプリセットとして保存し、ワンクリックで適用できるようにします。
バッチ処理の活用
複数の動画を同時に処理できる作業は、まとめて行います。
複数の素材の色補正、音量調整、ノイズ除去などは、一つずつではなく、すべて選択してまとめて適用します。書き出しも、複数の動画をキューに入れて夜間に一括処理します。
これにより、待ち時間を減らし、作業を効率化できます。
完璧主義を手放す
編集で最も時間を浪費するのが、完璧を追求しすぎることです。
80%の品質で投稿し、次の動画に進む方が、100%を目指して時間をかけるより、長期的には成長につながります。視聴者は、1〜2フレームのカットのずれを気にしません。テンポとストーリーの方がはるかに重要です。
「完璧な動画」ではなく「十分に良い動画を継続的に投稿する」ことを目指しましょう。
定期的なスキルアップ
編集技術は常に進化しています。定期的に新しいテクニックを学ぶことで、効率が向上し続けます。
YouTubeで「編集 時短テクニック」「〇〇(ソフト名) ショートカット」などを検索し、新しい方法を学びます。月に1つ、新しいテクニックを習得する目標を立てます。
オンラインコースやチュートリアルに投資することも、長期的には編集時間の短縮につながります。
カット編集の判断基準とテンポの作り方
どこをカットするか、どこを残すかの判断基準を明確にすることで、迷う時間が減り、編集が速くなります。
カットすべき部分の明確な基準
以下の部分は、基本的にすべてカットします。
話し始める前の長い沈黙(3秒以上)、明らかな言い間違いとその訂正、「えー」「あー」などのフィラー音(多すぎる場合)、話が大きく脱線した部分、撮影中のトラブルや中断、無意味な長い間、話の重複(同じことを2回言っている)などです。
これらを機械的にカットすることで、判断に迷う時間が減ります。
残すべき「間」の判断
すべての沈黙をカットするのではなく、意味のある「間」は残します。
重要なポイントの前の短い間(1〜2秒)は、視聴者に考える時間を与えます。感情を表現する間、笑いを誘う間、場面転換の間などは、動画のリズムを作る重要な要素です。
完全に間をなくすと、息苦しく、機械的な動画になります。視聴者が情報を消化できる適度な間を残すことが重要です。
ジャンプカットの活用
ジャンプカット(同じアングルで時間が飛ぶカット)は、YouTubeで非常に効果的な技法です。
カット部分を隠そうとせず、大胆にジャンプカットすることで、テンポの良い動画になります。視聴者は、ジャンプカットに慣れており、違和感を感じません。
トランジション(画面切り替え効果)でカットを隠そうとすると、時間がかかり、かえって不自然になることがあります。
リズムとテンポの意識
動画全体のリズムを意識してカットします。
速いテンポのセクション(情報を詰め込む部分)と、ゆっくりしたセクション(重要な説明、感情的な部分)を交互に配置します。単調なテンポは視聴者を飽きさせます。変化を持たせることが重要です。
音楽のビートに合わせてカットすると、リズミカルで心地よい動画になります。
よくある質問とトラブルシューティング
カット編集の効率化に関するよくある疑問と問題の解決方法を紹介します。
Q1:どのくらいカットすれば適切?
一般的に、撮影素材の30〜50%をカットすると言われています。10分撮影して、5〜7分の動画になるイメージです。
ただし、これはジャンルやスタイルによって大きく異なります。テンポ重視の解説動画では50%以上カット、ゆったりしたVlogでは20%程度のカットということもあります。
重要なのは、視聴維持率を見て判断することです。視聴者が途中で離脱する部分は、テンポが遅すぎる可能性があります。
Q2:カットが多すぎて不自然にならないか?
現代のYouTube視聴者は、カットの多い動画に慣れています。むしろ、カットが少なく冗長な動画の方が、視聴者を失います。
ただし、カットのタイミングが不自然だと違和感があります。話の途中で切らず、文や節の区切りでカットすること、呼吸や自然な間のタイミングでカットすることが重要です。
Q3:編集に何時間かけるべき?
目安として、10分の動画に対して2〜4時間の編集時間が一般的です。慣れてくれば、1〜2時間まで短縮できます。
ただし、エフェクトやアニメーションを多用する動画では、さらに時間がかかります。重要なのは、完璧を目指しすぎないことです。
Q4:カットのミスを見つけた場合、どこまで修正する?
完璧を目指すと無限に時間がかかります。明らかなミス(音声が切れている、話が繋がっていない)は修正しますが、1〜2フレームのずれなどは、視聴者は気づきません。
「公開後に気づいても修正しない」というルールを自分に課すことで、完璧主義を手放せます。
Q5:他のYouTuberはどうやって速く編集している?
人気YouTuberの多くは、以下の方法で効率化しています。
編集アシスタントを雇う(外注する)、撮影時点で編集を意識する(無駄な撮影を減らす)、テンプレートを徹底活用する、ショートカットを完全に習得している、同じフォーマットの動画を繰り返し作る(ルーティン化)などです。
個人でできる範囲で、これらの方法を取り入れましょう。
Q6:編集を外注すべきタイミングは?
チャンネルが成長し、以下の条件を満たしたら外注を検討します。
編集に週20時間以上かけている、編集のせいで投稿頻度が落ちている、収益が安定している(月10万円以上)、企画や撮影により多くの時間を使いたい場合などです。
外注コストは、1本5000円〜30000円程度が相場です。
Q7:撮影時に気をつけることで編集を効率化できる?
はい、撮影段階での工夫が編集時間を大きく左右します。
台本やアウトラインを準備し、無駄な撮影を減らす、言い間違えたらすぐにその場で撮り直す、撮影開始時に手を叩く(音声波形で編集ポイントが分かりやすい)、カメラを止めずに複数テイクを撮る(後で選択しやすい)などが有効です。
まとめ:効率化で持続可能なYouTube活動を
YouTubeのカット編集を効率化する方法について、キーボードショートカットの活用、効率的なワークフロー、自動化ツールの利用、判断基準の明確化、編集環境とマインドセットまで詳しく解説しました。
重要なポイントをまとめると、J・K・L、I・O、リップル削除のショートカットを習得するだけで速度が倍増すること、粗編集と精密編集を分離することで全体像を把握しながら効率的に進められること、無音・フィラー音の自動検出ツールを活用すれば時間が劇的に短縮されること、完璧主義を手放し80%の品質で継続投稿する方が長期的に成功すること、そして撮影時点での工夫が編集時間を大きく左右することです。
カット編集の効率化は、一朝一夕には身につきませんが、意識的に練習することで確実にスキルアップします。最初は1本の動画に10時間かかっていた人が、3ヶ月後には3時間で編集できるようになることは珍しくありません。効率化により生まれた時間を、より良い企画、質の高い撮影、視聴者とのコミュニケーションに使うことで、チャンネル全体の成長が加速します。持続可能なYouTube活動のために、編集効率化に投資しましょう。
より詳しく学びたい方へ
この記事は、AIラボコミュニティの運営者が執筆しています。
YouTubeのカット編集効率化をはじめ、動画制作の全プロセス、編集ソフトの使いこなし方、ワークフロー最適化、時短テクニックについて、さらに深く学びたい方のために、AIラボでは無料のコミュニティを運営しています。実際に使用している効率化テクニックの共有や、編集で困ったときの相談、ショートカット一覧の配布など、実践的な情報を仲間と共に学べる場として、気軽にご参加いただけます。
人生を豊かにする今しかできないAI革命時代の新しい稼ぎ方では、YouTubeチャンネルの立ち上げから収益化、そして継続的なコンテンツ制作まで、包括的な戦略を解説しています。
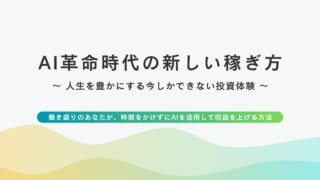
また、オープンチャット(あいラボコミュニティ:無料)では、同じようにYouTubeコンテンツ制作に取り組んでいる仲間たちと、編集効率化のコツや時短テクニックを共有できます。自分の編集ワークフローを見直したり、他のクリエイターの工夫から学んだりできる、生産性向上を支援する環境です。



